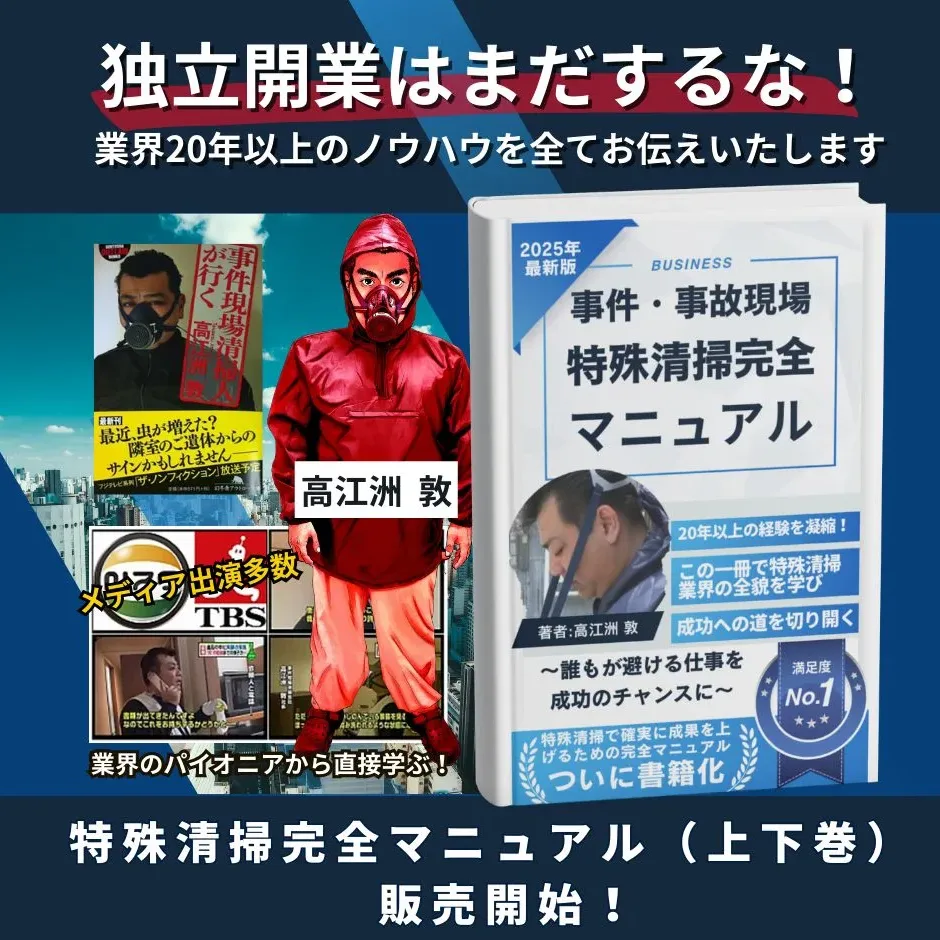こんにちは。高江洲敦です。
今回は、僕が「特殊清掃」という仕事を始めて間もないころ、
初めて現場に入ったときのことをお話しさせてください。
もしこれを読んでくださっているあなたが、
この仕事に少しでも関心を持っているのなら──
きっと、なにかの参考になると思います。
あの日、いつもとは違う空気を感じた
それは、ある夏の昼下がりでした。
葬儀会社の社長さんから、一本の電話が入りました。
「都内のワンルームマンションで、孤独死があった。
高江洲さん、入ってもらえないか?」
電話の向こうの声は淡々としていたけれど、
僕の心はザワついていました。
特殊清掃を始めたばかりのころのことです。
知識はあっても、経験はゼロ。
「亡くなった方がいる部屋に入る」という行為そのものに、
正直、強い恐怖を感じていました。
それでも、「やる」と答えたのは、
逃げ場がなかったからかもしれません。
当時、借金もあり、仕事を断れる立場ではありませんでした。
ドアの向こうにあったもの
現場に着いて、防護服を着て、
ドアノブに手をかけるまでに何度も深呼吸しました。
そして、ドアを開けた瞬間──
鼻を突く、強烈な臭い。
生臭さと腐敗臭が混じったような、今までに経験したことのない感覚。
部屋の中には、
生活の痕跡がそのまま残っていました。
コンビニの弁当、読みかけの新聞、冷蔵庫のモーター音。
そして──
畳に広がった黒い染み。
壁には、乾いた体液の飛び散った跡。
「ここで、誰かの人生が終わったんだ。」
その現実が、部屋の空気全体から伝わってきて、
僕は立ち尽くしてしまいました。
15分で、逃げ帰ったあの日
持っていた消臭剤を、言われたとおりにスプレーして、
一応、床や壁を少し拭いてみました。
でも、心がまったく追いついていなかった。
臭い、光景、音──
全てが想像を超えていて、
「自分には無理だ」と思いました。
作業を始めてから、わずか15分ほど。
僕は「今日はここまでで……」と、現場を後にしました。
肩で息をしながら、防護服を脱いだとき、
情けなくて、涙が出そうになったのを覚えています。
それでも、「また来よう」と思えた理由
でも、その日の夜。
どうしても、あの現場が頭から離れませんでした。
誰かが亡くなり、
誰にも看取られず、
ひとりで息を引き取ったその部屋を、
今、自分が見てきたのだ。
そう思ったとき──
不思議と、もう一度行きたいと思ったんです。
「もし自分が逃げ出さずに、あの部屋をきちんと片付けられたら。
残された誰かの助けになるんじゃないか。」
そんな想いが、心の奥に芽生えていました。
特殊清掃は、誰かのためにある
あの日、現場から逃げた自分を恥じていたけれど、
今思えば、あの15分間こそが、
僕の特殊清掃人としての原点だったのだと思います。
あの経験がなければ、
この仕事に、ここまで本気にはなれなかった。
「怖かった」という感情も、「無力だった」という悔しさも、
すべてが僕にとって、大切なスタート地点でした。
最後に
特殊清掃の現場には、
静かに消えていった命が、
確かにそこに存在したという証が、残っています。
それを、ただの「作業」として片付けるのではなく、
一つの人生と向き合う行為として、
これからも大切にしていきたいと、心から思っています。
読んでくださって、ありがとうございました。